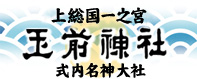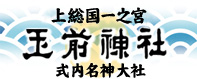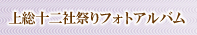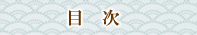無形民俗文化財「上総十二社祭り」
無形民俗文化財「上総十二社祭り」
平城天皇の御代・大同二年(807)創始と伝えられるこのお祭りはご祭神玉依姫命とその一族の神々が由縁の釣ヶ崎(つりがさき)海岸で年に一度再会されるという壮大な儀礼です。
房総半島に多い浜降り神事の中でも最古の歴史と伝統を誇り、意義深い古儀を今に伝える貴重なおまつりとして一宮町の無形民俗文化財に指定されています。
九月十日 鵜羽神社(うばじんじゃ)お迎え祭
鵜羽神社のご例祭の後、二基のお神輿(みこし)を玉前神社をお迎えします。
この
※1ご神幸(じんこう)は神代(かみよ)より伝わる龍神臨幸(りゅうぐうりんこう)の儀式といわれる古儀です。 (現在は三年に一度となっています) ご本殿に鵜羽神社のお神輿を入れて玉前神社の神様との御霊(みたま)合わせの儀式が行われます。
午後からは上総神楽(かずさかぐら)が奏されるなか、子育てのご神徳にあやかり稚児(ちご)行列に宮参りや神輿くぐり、また
※2ご祭神ゆかりの甘酒が振舞われるなど境内は子供たちで賑わいます。